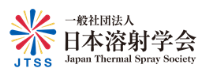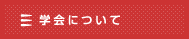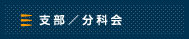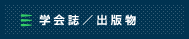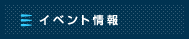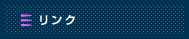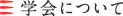溶射管理士 資格認定試験の受験を検討している人へ
溶射管理士資格認定試験は,
1stステップ:8月初旬に開催される4日間の講習会に参加
2ndステップ:10月初旬の認定試験に受験
→各科目(基礎科目5教科+専門科目3教科)に合格すると「溶射管理士」として認定されます.
基礎科目は,「安全衛生」,「溶射総論・製図」,「材料工学I」,「材料工学Ⅱ」,「品質管理」の5教科.
専門科目は,セラミック,サーメット,金属,防食の4部門から1部門を選択し,各専門の「特性/応用事例」,「材料/溶射法」,「試験検査法」の3教科.
8月初旬に開催される講習会では,「溶射技術入門(三訂版)」及び「溶射工学便覧(改訂版)」をテキストとして使用し,両テキストの内容を解説,講習します.5教科の基礎科目と3教科の専門科目の試験も講習の内容(両テキスト)から出題されます.
講習会では,普段,工学,材料工学,溶射技術に慣れ親しんでいない人でも,各教科の試験に不安に感じる人にも,初歩的な内容(例えば,専門用語の解説等)から講義しますので,積極的に溶射管理士にチャレンジしてもらいたいと考えております.
過去の試験問題(過去問)は,事務局で販売しております.また,出題された問題の一部は,解答例と解説と共に「溶射管理士資格認定試験 問題と解説」として学会事務局にて販売しております.購入を希望される方は事務局にご連絡ください.
<各科目の講義概要>
1.基礎科目
溶射総論・製図法 溶射工学全般にわたる概説を述べる。溶射の原理、溶射法と他のコーティング技術との比較による溶射法の特徴、溶射粒子の加熱・加速、溶射皮膜の構造的な特徴と皮膜特性などについて解説する.つぎに一般的な溶射加工法として、(1)前処理、(2)溶射施工、(3)後処理の概要を示し、最後に代表的な溶射装置について解説する. また溶射加工において必要とされる投影図の原理や溶射皮膜の記号など必要な範囲で機械製図の基礎について解説する.
材料工学Ⅰ 材料の基礎として原子の構造と元素、化学結合、原子の立体構造について示し、次に材料組織として主に金属材料の構造の一般論と、さまざまな相図について説明するとともに、相図に基づき金属材料における特徴的な組織の発現について解説する.
材料工学Ⅱ 材料の強さについて応力と変形、さらに内部での転位構造について説明し、金属材料における強化法について解説する。またセラミック材料の特徴とその破壊様式、破壊靭性について解説するとともに、摩耗現象、残留応力、疲労現象について述べる.
品質管理 溶射施工に関連するデータの処理方法としてのヒストグラムの作り方、標準偏差の導き方、正規分布及び管理図とその見方について解説する.
安全衛生 溶射加工作業に関わる安全衛生に関して、労働安全衛生の考え方と関連法規、安全な作業のための注意、危険物・有害物の取扱い上の注意、さらに作業員を守る保護具の利用法や注意点について、関係する事故事例などをまじえて解説する.
2.専門科目(各専門科目に共通する講義の概要を示しますが、専門科目ごとにその内容は多少変わります)
特性/応用事例 各専門科目に関係する溶射皮膜(セラミック、サーメット、金属、防食金属)の特徴を述べ、それぞれの応用における組織と特性の関連についてに応用事例を示しながら解説する.
材料/溶射法 溶射加工に必要な溶射装置について解説し、必要な溶射材料の特性と溶射皮膜の特性について解説する.さらに日本産業規格(JIS)に準拠した具体的な溶射施工プロセスについて詳述する.
試験検査法 各溶射材料に特徴的な評価とJISで求められる品質を評価するための試験検査法について解説するとともに、各専門の溶射皮膜を評価するさまざまな試験法について述べる.